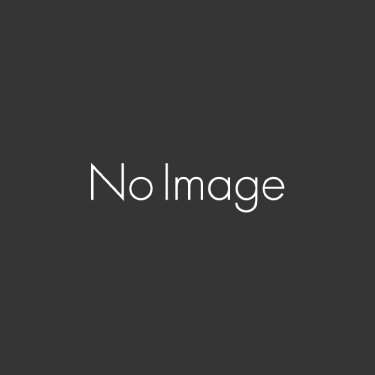あいさつ
1:1 私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリスト・イエスとの命令による、キリスト・イエスの使徒パウロから、
1:2 信仰による真実のわが子テモテへ。父なる神と私たちの主なるキリスト・イエスから、恵みとあわれみと平安とがありますように。
教会員たちを偽りの教えから守りなさい
1:3 私がマケドニヤに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたは、エペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、
1:4 果てしのない空想話と系図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは、論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。
パウロとテモテは度々共に伝道旅行をしました。そして彼らは、この時エペソにいたのではないかと思われます。パウロはエペソからマケドニヤに向うことになったパウロは、テモテをエペソに残して牧会させることにしたのです。その理由は、エペソ教会を混乱させていた「偽りの教え」でした。(3)
旧約聖書を「道徳を教える物語」として理解し(空想話、寓話的)、信仰によって与えられる義ではなく、律法に従うことによって勝ち取る義を強調し、信者を律法主義に傾かせる教師がいたと思われます。また別の教師は、キリストによって明らかにされた神の啓示をないがしろにして、旧約聖書に書かれた系図の詳細な研究を重視して、「救い主についての誤った理解」を導きだし、人々を説得していたのではないかと思われます。
正しい信仰が多くの証拠と証言によってその正当性が証明されているのに反して、これらは確かな証拠がありませ。なぜなら、所詮人が作りだした空想話に過ぎないからです。これらを探求しても、果てしない議論に終わるだけです。信仰によって救われるという神のご計画とはなんの関わりもありません。(4)
牧会の目標(ゴール)は信徒たちに正しい信仰をもたせ、愛の実を実らせること、無益な議論のために時間を無駄にするな。
1:5 この命令は、きよい心と正しい良心と偽りのない信仰とから出て来る愛を、目標としています。
信徒達を偽りの教えから遠ざけなさい。また、知恵があるように聞こえるけれども「救い」とは関係のないことを議論して彼らが時間を浪費することがないようにしなさい。
この命令を実行することによって、信徒たちに神の前に清い良心を持つことができるように指導し、神に対して真実な信仰を持たせるように務めなさい。その結果として、彼らの人格や生活に「愛の実」が現れるようになることが、牧会の目標です。
誤った教師たち
彼らはキリスト者に対する律法の役割を誤って理解している。
1:6 ある人たちはこの目当てを見失い、わき道にそれて無益な議論に走り、
1:7 律法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。
1:8 しかし私たちは知っています。律法は、もし次のことを知っていて正しく用いるならば、良いものです。
1:9 すなわち、律法は、正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、
1:10 不品行な者、男色をする者、人を誘拐する者、うそをつく者、偽証をする者などのため、またそのほか健全な教えにそむく事のためにあるのです。
1:11 祝福に満ちた神の、栄光の福音によれば、こうなのであって、私はその福音をゆだねられたのです。
牧会の目標は、信徒達に純粋な信仰を持たせ、愛の実を実らせることです。
しかし、ある教師達は、本来の目標からそれて、系図についての研究や聖書を人間が作り上げた物語として教え、神の前に偽りのない信仰が持てないようにしています。(6)
彼らは、自分たちが人々に正しい行ないができるように教える教師でありたいと願いながら、実はそれができていないのです。なぜなら、真実な信仰を教えることができなければ、そこから生じる愛の実を信徒たちに実らせることはできないからです。(7)
律法は、正しく行っている人を誉めるためにあるのではなく、悪い行ないをする人や、神の教えに従わない人を罪に定めるためにあるのです。(9、10)
律法の役割について正しく知って用いることが牧会者には要求されます。特にキリスト者と律法の関係について正しく知ることは重要です。ですから律法を正しく教える教師でありたいと願っていたにもかかわらず、彼らは律法を誤って理解していたために、信徒たちに誤って律法を適応していたのです。
神が自分を救ってくださったことへの感謝(パウロ)
1:12 私は、私を強くしてくださる私たちの主キリスト・イエスに感謝をささげています。なぜなら、キリストは、私をこの務めに任命して、私を忠実な者と認めてくださったからです。
1:13 私は以前は、神をけがす者、迫害する者、暴力をふるう者でした。それでも、信じていないときに知らないでしたことなので、あわれみを受けたのです。
1:14 私たちの主の、この恵みは、キリスト・イエスにある信仰と愛とともに、ますます満ちあふれるようになりました。
神に敵対していた私を、使徒の務めに任命してくださったことを神に感謝する。
パウロは救われる前、父なる神の化身がキリストであることを否定して、キリスト教会を迫害しました。つまり神をけがす者、暴力をふるう者でした。
そのような彼に、神は信頼できる働き人として認めて、使徒の務めを与えてくださったのです。ですからパウロの神に対する感謝は尽きません。
しかし、この感謝はパウロだけではなく、神から救いが与えられる全ての人に共通の感情です。なぜなら、全ての人は罪を犯して、神からの栄誉を受けることができなくなっており、神を否定して自分勝手な生き方をしているからです。神はこれらの恵みを授ける価のない者達を選び、救いを与え、天国を相続する権利をお与えになるからです。(12,13)
神はご自身が選んだつみびとに信仰を与え、愛を注ぎます。神の恵みを注がれた者達は、この世にその恵みを反射していきます。人々に信仰を伝え、自分が神から受けた愛を持って、人々を愛していきます。(14)
1:15 「キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世に来られた。」ということばは、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人のかしらです。
1:16 しかし、そのような私があわれみを受けたのは、イエス・キリストが、今後彼を信じて永遠のいのちを得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。
1:17 どうか、世々の王、すなわち、滅びることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。
私は神の教会を迫害していた。その私に救いが与えられた理由は、罪深い者でも信じれば救われることを、後生に示すためであった。
キリストは、正しい人のためではなく、罪人を救うために来られたということは真実です。その証拠として、パウロのように一番先頭に立って教会を迫害していた者が救われ、使徒に任命されたからです。
パウロは自分が罪人であることを深く自覚していました。彼の罪意識は、律法学者であった時に、教会に対して犯した罪に対する後悔だけではありません。彼の存在自体が罪に犯されているという深い罪の自覚でした。(15)
しかし、罪人が神のあわれみによって救われるということを、世に明らかにするための見本として、神はパウロのように神に敵対する人間を選んで救ったのです。(16)
私たちの救いは神によります。この神に栄光が永遠にありますように。(17)
テモテに勇敢に戦うように勧める
1:18 私の子テモテよ。以前あなたについてなされた預言に従って、私はあなたにこの命令をゆだねます。それは、あなたがあの預言によって、信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。
テモテはパウロから按手を受けた時、賜物を受けました。(Ⅱテモテ1:6)
それ以外の機会かもしれませんが、彼は神から預言をいただいていました。
おそらく、彼が確かに働き人として神から任命されたことを保証する預言であったのでしょう。
牧会は信仰の戦いを通してなされます。時には忍耐を要する困難な仕事です。疲れ果てることもあるでしょう。そのような時に、自分が神の召しを受けてこの務めに当たっていることを思い起こすことは、良い事です。起こっている状況から目を離し、神が始められた働きであるから、神が完成してくださるであろうと安心することができるからです。
パウロは牧会の大変さをよく分かっていました。パウロ自身も、困難な時、自分の召しのことを思い起こしていたのかもしれません。
1:19 ある人たちは、正しい良心を捨てて、信仰の破船に会いました。
1:20 その中には、ヒメナオとアレキサンデルがいます。私は、彼らをサタンに引き渡しました。それは、神をけがしてはならないことを、彼らに学ばせるためです
エペソの教会には、教会戒規が実行され、交わりから断たれた兄弟たちがいたようです。それがヒメナオとアレキサンデルでした。
彼らが、正しい信仰に立ち帰ることを願って、厳しい処罰がなされたのでした。
<この手紙が書かれた背景>
テモテへの手紙の特徴
テモテ、テトスへの手紙は「牧会の手紙」と呼ばれています。その特徴は、
1.教会ではなく、牧師に直接差し出された手紙である。
2.神学的なことよりも、教会生活の実際的な指導法が書かれている。
(礼拝の秩序、役員の資格、登録すべきやもめの問題等、牧会に関わる事)
3.偽りの教えから教会を守ることが強調されている。(牧師の重要な務め)
当時は、このような手紙が多く行きかっていたと思われます。
この手紙で問題にされている異端とは何か
「グノーシス」は2世紀に広まったキリスト教の異端です。
グノーシスは、なぜこの世に悪が存在するのかを、霊肉2元論で説明します。
アイオーン界(天上界)の最高神とアイオーン(霊であり善の存在)の1つが堕落した地上界の被造物デミウゴス(肉体、物質である悪なる存在)を考えました。
人間を、霊的、感覚的、肉体的、霊的の4つに区別しました。
霊的なものがすぐれており、肉体や物質は堕落しており悪であると考えました。
そして、霊的人間のみがすぐれていて救われるとしました。
道徳的には、厳格な禁欲主義か、肉体を軽んじる放蕩の2極に分かれます。
キリストについては、肉体を悪とみなすため、「仮現論」を主張しました。
「仮現論」とは何か
しかし、グノーシスが広まったのは2世紀に入ってからでした。この手紙は紀元65年頃書かれたため、この手紙で言及されている偽りの教えは「グノーシス主義」のことではないと思われます。おそらく、ユダヤ人教師たちによる「律法主義」が主な問題であったのではないでしょうか。彼らは信仰ではなく、行ないによる救いや、行ないによる報いを強調したのではないかと思います。
この手紙が書かれた時期
この手紙は、パウロがローマの幽閉(61-63)から解放されて、かつて伝道したところを巡っていた時に書かれたものだと思われます。
<第2テサロニケ3章 考察>
考察1 牧会者は牧会の目標を見誤ってはならない。
牧会の目標は、信徒を異端から守り、愛の実を実らせるまでに成長させることである。4節から6節より
牧会の目標は、信徒に真実な信仰を持たせること、信徒たちの人格に、また行ないに、愛が実ることです。
牧会の目標を達成するためには、正しい信仰を伝え、偽りの教えが教会に入り込まないようにしなければなりません。また、知ったとしても救いとは関係がなく、結論が出ないため延々と続く議論のために、信徒たちが力を浪費することがないようにし、本当に学ぶべき事柄に思いを向けさせることが必要です。
牧師が、牧会の目標を見誤る時、信徒は信仰の破綻に会います。
牧会の目標が、牧師自身の才能を人に認めさせるためである場合、テモテ1章 に書かれてあるように、系図の研究など、聖書の中心から外れた、人が知らない知識を掘り起こして議論するようになってしまいます。
また、牧会の目標がとにかく信徒を励ますことである場合は、
神の愛と赦しのご人格のみを伝えることになり、その結果として信徒たち真実の信仰を持つことができず、愛の実を実らせることもありません。
職場や家庭での不満(多くの場合自分の罪の結果を刈り取っているのだが)を解消するために教会で集まっているだけになります。
ですから、牧師は牧会の目標を正しく見据えて信徒たちを指導しなければなりません。
神のご性質のすべての面を教え、信徒たちに真実な信仰を持たせる努力をしなければなりません。
家庭や職場での彼らのあり方や、彼ら自身の人格に良い変化が現れることを願って、真剣に彼らを教え、戒め、導かなければなりません。
教会の方向性を決める権限を持つ牧会者や役員たちは、このことについて、自分たちの教会を真剣に吟味して見る必要があると思われます。
考察2 聖書を「教訓を教える物語」(寓話)として解釈する信仰は偽りの信仰。聖書を神の言葉として理解し、実際に起こったこととして理解しなければ、愛の実を生じることはできない。 4節から
エペソの教会には、聖書の記述を事実としてではなく、良い生き方を教えるために書かれた物語として解釈する人々がいました。現代で言うならば、「自由主義神学」です。聖書の無謬性(統一性)、逐語霊感性(1語1語が神の霊感によって書かれた)ことを否定し、人間が聖書を読んで感じたこと、考えたことが大事だとする神学です。
たとえば、「イエスが水の上を歩いた」ことを事実としてとらえるのではなく、
「水の上を歩いた」という表現から、聖書が何を伝えたかったのかと考えるのです。水は何のたとえか?歩くとは人生の歩みか?など果てしなく想像を広げていって、そこから生きるための教訓を引き出すのです。
このような説教は、賢く聞こえますが、神に対する清い良心、偽りのない信仰は生まれません。なぜなら、神の全知、全能を否定し、神の言葉に疑いを持つ信仰は、神に頼らず自分の理性に頼る信仰だからです。
そしてそのような信仰は、愛も生じないのです。愛は、真実な信仰のみが産み出すものだからです。
御霊の実は、愛、寛容、柔和、親切、自制などの人格に実る実です。また、困っている者を助けるなどの行いに現れる実です。
このようにして、信仰と称して「神の権威」を落としめている人達は、御霊の実を結ぶこともなく、新生しない状態にとどまります。
ですから、牧会者は聖書の権威を認めて教える者でなければなりません。
聖書の無謬性、逐語霊感を支持して、聖書に書かれたことは事実起こったとして、説教しなければなりません。このことが、現在多くの教会で認められていないし、議論されていることが悲しいことです。
この節から言えることは、パウロは寓話的な解釈を認めていないということです。パウロは聖書はすべて神の霊感によって書かれており、聖書に書かれたことは事実であったと認めています。
パウロは神から直接啓示を受けた使徒ですから、パウロの意見は神のご意志であることを重く見て、教会は始めの福音に立ち帰らなければなりません。
考察3 説教者は、律法の正しい位置づけを理解している必要がある。
これは福音の中心である、これを外してはならない。
キリスト者と律法との関係 重要な3つのポイント
律法と救いの関係
- 律法自体は良いもの キリスト者は律法を否定していない。
- 律法は罪を明らかにするためにある
- 人間に罪を認めさせ天国には入れないことを自覚させるためにある
- 律法によっては救われない 罪の意識が深まるのみ
- 行ないによらず、信仰のみによって救われる
律法とキリスト者の関係
- キリスト者は律法によって裁かれない者になった
- 御霊によって、律法を全うする道が与えられた
- 自己を否んで自己に頼らず、御霊に頼って行ないを制御する
- 罪を犯しても赦されている。
- 罪の告白は、罪の赦しのためではなく、清い良心を回復するため。
- 自分の罪を認めるため、神の前に心の隔たりなく、神に祈り願うことができるようになるため
キリスト者にとって、自分が救われた時のことを思い出すことは益
- 神によって、信仰が与えられたことを確認すること
- 困難なとき、将来に不安を覚えるとき、この思いが支えてくれる
- 神によって始まった、神が責任を持って最後まで導いてくれる
- この問題も益に変えてくれると信じる。