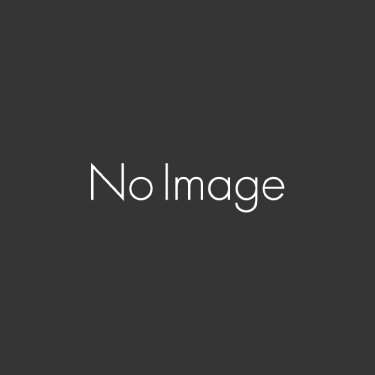すべての人の救いのためにとりなしの祈りを捧げなさい。
2:1 そこで、まず初めに、このことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感謝がささげられるようにしなさい。
2:2 それは、私たちが敬虔に、また、威厳をもって、平安で静かな一生を過ごすためです。
2:3 そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです
王や高い地位にある人のためにも祈りなさい。
ここでは、クリスチャンが為政者たちのためにも祈るように勧められています。
クリスチャンといえども、政府の統治の下で暮らしており、政府の方針によって、自分たちの命が左右される立場にあります。
ですから、信仰を続けることができ、安全に暮らしていくことができるように、為政者や未信者たちがクリスチャンに寛容であるように祈る必要があるのです。
もし、政府の高官が救われるなら、キリスト者の安全のために、彼らは政府に働きかけてくれます。
また、人々が救われてキリストの権威を認めるようになれば、信仰者の安全は守られます。
ですから、彼らは、為政者の救いのために、また未信者のために、神にとりなしの祈りを捧げるように、パウロは勧めたのではないかと思われます。
神は全ての人が救われて真理を知ることを願っておられる
2:4 神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。
2:5 神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリスト・イエスです。
2:6 キリストは、すべての人の贖いの代価として、ご自身をお与えになりました。これが時至ってなされたあかしなのです。
2:7 そのあかしのために、私は宣伝者また使徒に任じられ――私は真実を言っており、うそは言いません。――信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。
その真理とは、キリストについての正しい知識である。
4節に、「神が全ての人が救われて真理を知るようになることを願っている」と書かれています。「すべての人が救われる」とは書かれていません。
ここでは、パウロは単純に、神の願いを書いているだけです。
この箇所をこれ以上にも、またこれ以下にも理解して議論を展開するべきではありません。
そして、神が全ての人に知ってほしいと願う「真理」は、5節、6節に書かれています。それは、キリストについての正しい理解です。では、神が私たちに知ることを願っておられる真理について見て行きましょう。
- 第1に、神は唯一であること。偶像は神ではないこと。
- 第2に、人間は生まれつき神に敵対していること。
- 人は神と和解するために、キリストの仲介を必要とすること。
キリストのみが仲介の役目を果たすことができ、偶像にはできないこと。 - 第3に、キリストは、イエスという人になって、この世界に来られたこと。
つまり、イエスがキリストである。(人としてのキリスト) - 第4、キリストは突然現れたのではなく、その出現を前もって預言され、その出現のためにイスラエルの歴史を通して準備がなされていたこと。(時至ってなされたあかし)
- 第5に、キリストは人の罪のあがないをするために死なれたこと。
これらの真理をすべての人が知るようにと神は願っておられるので、キリスト者はすべての人のために「とりなしの祈り」をするのです。
4節で使われている「真理」(ギ:アレーセイア)はキリストにおける神の啓示全体、キリスト信仰の正統的教義を意味します。また、「知る」という言葉は、ギリシャ語で「エピグノーシス」が使われています。
これは異端である「グノーシス=知る」と区別するために、あえて使った言葉で、異端ではなく真理を受け取ることです。
ですから、4節の「すべての人が真理を知る」の解釈は、救われた全ての人が、誤った真理ではなく、正しい真理を知るように神が願っておられる」という意味に理解するべきです。
ですから、4.5.6節の「神がすべての人の救いを願っておられ、キリストがすべての人の贖いの代価としてご自身をささげられた」の聖句を、
「キリストの十字架は、信じないで死ぬ者をも含めた全人類のための罪のあがないであった」と解釈し、さらに「神はすべての人の罪のあがないを済ませておられるから、キリストを信じないで死んだ人も天国にいける」と結論することは間違っています。
そして4、5、6節を根拠として、「キリストの罪のあがないは、救われる人に限定されたものであった」とするカルバニズムの理解を否定することはできません。
このことについては、考察でもう少し詳しく書いていますので、ご覧下さい。
礼拝の場所における男女のふるまいについて
2:8 ですから、私は願うのです。男は、怒ったり言い争ったりすることなく、どこででもきよい手を上げて祈るようにしなさい。
男性に対しての注意
「どこででも」とは、公同の礼拝のために集まる所ではどこでもの意味です。
したがって、男性が教会で集まる時は、どのような機会であっても、感情的にならず、言い争うのではなく、まず神にその問題の答えを求めなさい。そのために、双方が祈りなさいという意味だと思われます。
2:9 同じように女も、つつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、はでな髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、
2:10 むしろ、神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行ないを自分の飾りとしなさい。
2:11 女は、静かにして、よく従う心をもって教えを受けなさい。
2:12 私は、女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ、静かにしていなさい。
2:13 アダムが初めに造られ、次にエバが造られたからです。
2:14 また、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、あやまちを犯しました。
2:15 しかし、女が慎みをもって、信仰と愛と聖さとを保つなら、子を産むことによって救われます。
女性に対しての注意
エペソ教会の女性たちの中に、身なりを飾り立て、性的魅力をアピールする者がいたようです。パウロは、女性は礼拝では、自分の性的魅力を隠すべきだと指導します。(9)
身を飾り立てるよりも、善い行ないを飾りとして身につけさないと言っています。(10)
「女性は静かにしていなさい」11節12節は難解な個所です。
パウロの時代の教会が現代の教会よりも理想的であったと考えてはいけません。
パウロが厳しい言葉で止めさせなければならなかったほど、ひどい女性たちが、エペソ教会にいたのです。
この言葉から、パウロが女性を低く見ていたとか、働き人になりえないと考えていたと結論づけてはいけません。ですからこの聖句を、そのまま現代の礼拝に適応することは無理があります。
また、パウロは当時としてははるかに進んだ女性観を持っていました。
パウロは手紙の最後に女性たちにあいさつを送り、ユウオデアとスントケを同労者と呼び、フィベを執事にして「私の姉妹」と呼んで大切な用事を任せているからです。
しかし、彼も時代の中で制約を受けている人でした。
その証拠に、一般に公同の礼拝においては女性は沈黙しているべきだと信じていたようです。
「エバが始めに惑わされた」ので、この世に罪が入ったのです。
ですから女性は、だまされやすいことを忘れてはいけません。
しかし「アダムがだまされなかった」と書かれているから、男性は罪を犯さない傾向があると言っているのではありません。
ここでは女性がだまされやすいと言う事実を端的に述べているにすぎません。
14節で「アダム」に対して「女」と書かれていることから、パウロがエペソ教会の女性たちを意識して言っていることがわかります。
エペソ教会で暴走する女性たちを静止する目的で書かれている個所です。
「女性は教会ではだまっていなさい」「女性は礼拝ではかぶりものをしなさい」
「女性は、男性に従いなさい」「女性は子を産むことによって救われる」
これらの聖句を、現代の教会に、そのまま適応することは無理があります。
その当時としては、習慣や文化に良く適合した指導のことばや、
その教会の状況に対して、適切な指導だった「ことば」が書かれている個所があるからです。
教会の姿、それは教会を取り巻く世界と全く無関係ではありません。
私たちは女性がいかなる形で教会に関わるべきかを、現代という状況をふまえて大いに考える必要があります。
時代に制約されている箇所を、現代に機械的に当てはめて適応することは、聖書的に見えて実はそうでないからです。
第1テモテ2章 考察
考察1「神はすべての人が救われて、真理をしることを願っておられる」4節
「キリストは、すべての人のあがないの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされたあかしなのです」6節
<この聖句から、カルバニズムとアルミニウスについて考える>
この聖句の理解については、カルバニズムとアルミニウスとの間で大きく意見が分かれます。
この聖句から、アルミニウス主義の人々は、「キリストはすべての人の罪を許すために死なれた。神もすべての人が救われることを願っておられる」と解釈します。
神は、救いのための準備を全人類のために成就して、どうぞ受け取ってくださいと人間に差し出しておられる。あとは人間がその救いを受けるか拒否するかにかかっていると言います。
つまり、アルミニウス主義によれば、救いを完成させるのは「人間」です。
ですから、人間が決心するための伝道がなされます。
集会では、説得の力、音楽や霊的な演出、などによって告白を促します。
また、未信者に援助したり、親しくなることによって、より多くの決心者を出そうとする伝道がなされます。
カルバニズムの場合は、この聖句を「救いは、神があらかじめ救いに定めておられたすべての人のためであった。」と理解します。
このところの聖句は、解釈のところで書きましたが、異端ではなく真理によって成長することを願う神のみこころが語られているからです。
「知る」ということばは、「エピグノーシス」で、グノーシス(異端)ではなく、エピグノーシス(真理)を知りなさいという言葉だからです。
さらに、キリストの証言、聖書全体を通しての啓示やパウロの理解が「神はすべての人を救うのではなく、天地創造以前から救いに定めた人を救う」と告げています。
事実、神に呼ばれた人は、たとえ抵抗したとしても、最後には神の召しに答えざるをえなくされることを、私たちは聖書の中に見ることができます。
たとえば、神の命令に逆らう「ヨナ」です。
知恵と策略に頼っていた「ヤコブ」、臆病で神の約束を何度も確かめた「ギデオン」・・彼らは初めから信仰の偉人ではありませんでした。
しかし、神の力が彼らに臨んだので、彼らは変えられました。
彼らは自分勝手な道に歩んでいました。
しかし、彼らとて神の被造物にすぎなかったので、神の召しに逆らい続けることはできず、最後には自ら進んで、「神のしもべ」と変えられて、神のために困難な任務を果たしたのです。
パウロの場合、ダマスコに行く途中で神からの声を聞いた時、彼には「キリストを信じたい」思いは全くありませんでした。
それどころか、彼は「キリスト者を迫害することが自分の使命である」とさえ確信していたのです。
神の力は、そのような彼でさえ「キリストの兵士」へと変えることができました。彼は全く変えられて、その後キリストのために命がけで働きました。
キリストも、救いは人間の選択によるのではなく、神のわざであることを証言しています。
「あなたがた私を選んだのではありません。私があなたがたを選び、あなたがたを任命したのです。」(ヨハネ15:16)
「わたしは、あなたが世から取り出してわたしに下さった人々に、あなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らをわたしに下さいました。」(ヨハネ17:6)
聖書全体の証言を通しても、救いが「人間の選択による」のではなく、「神の計画による」ことを見ることが出来ます。
神はイスラエル民族を選びご自身を彼らに知らせました。
しかし異邦人にはこの知識は長い間隠しておられました。
そして、キリストの復活以降、この知識が異邦人達にも伝えられたのです。
これらの証拠から言えることは、救いを決定するのは「人間の意志」ではなく、「神による」ということです。
カルバニズムは、「救いは神の選びによる」と理解します。
神からの召しが与えられた人は、その召しに抵抗することができないで、自分から進んで神の意志に従う決心をするということです。
これがカルバニズムの救いについての理解です。
この理解から、カルバニズム伝道の方法が導かれます。
それは、人の機嫌を損ねることを恐れないで、真理を大胆に伝えることです。
人は「神について」聞くこと無しに救われることはないからです。
その際、神についての正しい理解を伝えることが出来なければなりません。
そのために伝道する者は、聖書をよく学び、正しい信仰を実践していなければなりません。
また、人々が信じるために、人々に聖霊が働かれるように祈ることです。
つまり、「とりなしの祈り」を捧げることが重要です。
たとえ福音を聞いて受入れない人であっても、神が恵みを与えてくだされば変わるのです。
この信仰をもって、伝え続けることが重要になります。
カルバニズムを指示する人は、聖霊の働きを祈りつつ伝道を進めてていきます。
彼らの伝道スタイルは、地味です。
聖書を開いて、みことばから大胆に真理を語る。
人間的なものが、みことばを聞いた人の信仰の告白を左右することがないように気をつける。
具体的に言えば、その場の雰囲気や人間的な情、伝える人への恩返しの気持ちなどが、「信仰の決心」に影響しないように心がけます。
そして、人がみことばを聞くことを通して、神と個人的に出会い、自ら進んで信じる決心をすることを願うのです。
今までアルミニウスとカルバニズムの違いについて書いてきました。「どちらでもいいじゃないか、大きな違いではない」と思う方がおられるかもしれません。しかし、この2つの理解は、伝道方法の違いを生み出し、救われた後の信仰の保証(一度救われれば、救いを失うことはない)にまで影響する重大な違いなのです。
アルミニウスの立場から「救いの保証」について説明するならば、救いは人間の意志次第であり、天国に入る確信を持つことはできない」ということになります。なぜなら、人間の意志が救いを最終的に決定するので、人間の気持ちが変われば救いを失うこともあるのです。
ただ、死ぬ瞬間に信仰を選んでいた人だけが、救われて天国に行くことになります。
アルミニウス主義では、信仰者は生きている間に、救いの確信を持つことはできません。常に救われているかどうか不安な状態におかれることになります。
アルミニウスの立場をとる人たちは、第一テモテ2章4-6節を、彼らの立場を支持する聖句だとして主張してきました。しかし、上記で証明したように、彼らの理解は誤っています。
神は、救いのための準備ができるだけで、ただじっと人間が救いを受け取ってくれるのを待っているだけの、力のない方ではありません。
神は、自分で救いを得ることができない、破滅に向かうしかない人間に、救いを与えることができる力づよい方です。
神は全能であり、救おうと思う者を救うことがおできになります。
そして、ご自分が救った者を、ご自身の約束のゆえに、最後までその信仰を守り、天国に入れる方です。
アルミニウスの立場は、信仰者を自分の意志や努力に頼らせ、神のみわざに安息することをゆるしません+。
ですから、信者にとって、アルミニウスかカルバニズムか、どちらの立場を取るのかはどうでもいい問題ではなく、非常に重要な問題です。
私たちは、たとえ少数派であったとしても、カルバニズムの立場に固く立ち、後世に伝えていかなければなりません。